第9回JMC海事振興セミナー
「国際海運におけるチョークポイントの動向と海上コンテナ輸送への影響」
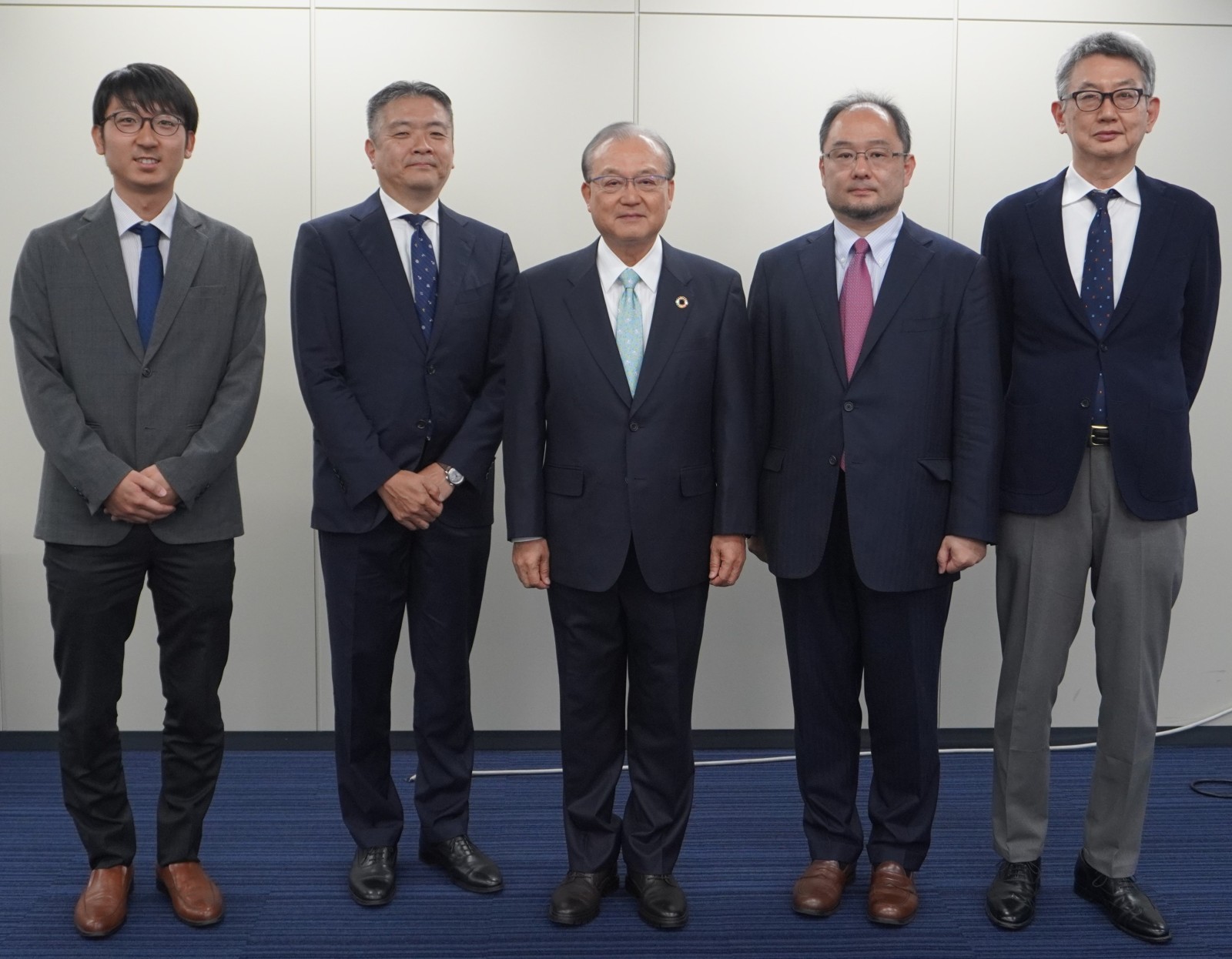 |
|
 |
|
| 開催概要 | 昨年11月にフーシ派による自動車専用船のハイジャックが発生し、現在に至るまで紅海周辺での商船への攻撃が続いており、多くの船舶が紅海の航行を避けている。また、パナマ運河では昨年来水不足が問題となり、通航隻数や喫水の制限が強化されるなど2大運河における船舶の航行に支障が生じている状態である。 本セミナーでは、スエズ運河、パナマ運河等のチョークポイントの動向に関する日本海事センターからの報告に加え、各種統計や文献から現在の海上コンテナ輸送における需要・供給面の動向、紅海情勢を中心に海上輸送を取り巻く環境の変化や事業者の対応ならびに今後の展望等について日本郵船調査グループからご講演をいただき、情報の把握や知見を深めることを目的とする。 |
| 日時 | 2024年5月9日(木) 14:00 ~ 16:00 |
| 開催方法 | ハイブリッド形式(Zoomウェビナー併用) |
| 場所 | 海事センタービル4階会議室 (〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5) |
| 開会挨拶 | |
| 講演1 |
 |
| 講演2 |
 |
| 講演者との鼎談 | |
| 閉会挨拶 | |
| セミナー動画 (通し) |
https://www.youtube.com/watch?v=V2mKnpjmqPc |
第9回JMC海事振興セミナーの開催結果(概要)
1.開催の概要
令和6年5月9日、東京都千代田区麹町の海事センタービル4階会議室において、第9回JMC海事振興セミナーを開催した。
当日は、「国際海運におけるチョークポイントの動向と海上コンテナ輸送への影響」と題して、ZOOMを活用したオンライン配信を実施し、600名を超える視聴者から参加登録をいただき、盛況裡の開催となった。
2.講演内容
「国際海運におけるチョークポイントの動向についてースエズ運河、パナマ運河を中心にー」
日本海事センター 企画研究部 研究員 後藤 洋政
国際海運におけるチョークポイントの動向について、スエズ運河およびパナマ運河の概要や通航実績を報告したうえで、スエズ運河に関しては中東情勢の変化、パナマ運河に関しては水不足による船舶通航への影響をそれぞれ説明した。
また、マラッカ・シンガポール海峡、ホルムズ海峡、台湾海峡、北極海航路について資料に基づき報告し、両運河での通航に制約が生じている状況を関連する事業者は所与のものとして対応しており、海上輸送路の安全確保は貿易などの経済活動における重要な要素であり、安定的通航が求められると述べた。
「海上コンテナ輸送の現状、事業者の対応、今後の展望」
日本郵船株式会社 調査グループ グループ長代理 原 源太郎氏
はじめに、海上コンテナ輸送における外部環境の変化として、国際情勢や地球環境ならびにグローバルバリューチェーン(GVC)を挙げ、この変化に応じて海運会社や荷主の行動が規定される点を説明した。
次いで、紅海情勢については、喜望峰への迂回に関してONEの事例をはじめとした海運会社の対応を紹介、航海距離の増加による船腹需要の拡大に対して、供給船腹量とのギャップがある点を説明した。
さらにインド中東地域の荷動きが増加していることを指摘し、GVCの変化に伴うインド発着貨物増加の背景や過去のネットワークの変化ならびに成長の見通しを説明した。
加えて、アライアンスの再編に関し、ネットワーク理論による各アライアンスの航路網を分析した研究結果を説明し、マースクとハパッグロイドによるGEMINI Cooperationを含めた2025年2月以降の航路網についても見通しを述べた。
最後に、中国発米国向けコンテナ貨物の増加について、経済指標だけでは説明できず、 ウォルマートの在庫率の分析等をふまえ、ピーク時の対応を含め実需に加えた要因があると指摘し、改めて外部環境の変化に規定される海運会社と荷主の行動とその相互作用によって海上コンテナ輸送は変動するとまとめた。
3.講演者との鼎談
モデレーター:拓殖大学商学部 教授(日本海事センター客員研究員)松田 琢磨氏
モデレーターが講演内容を整理して要点を説明したのち、事前質問フォームからの投稿をふまえ、以下のとおり鼎談が行われた。
・スエズ運河を通航しない船舶が増加したことによるエジプト政府の対応等はどのようなものか。
後藤
スエズ運河庁は2022年、23年に続いて、昨年のアナウンス通り今年1月に通航料を引き上げた。一方でエジプトの主要な外貨収入源である通航料収入は減少しており、ロシア・ウクライナ戦争に伴うインフレ等経済状況の悪化もふまえ、IMFやEUはエジプトへの財政支援を発表した。エジプト政府はイラン・イスラエルに対立激化を避けるよう自制を促しており、ガザでの停戦を呼びかけている。
・中国系の船社はフーシ派の攻撃対象となっておらず、通航を継続しているという報道があった。実態はどうか。
後藤
バブ・エル・マンデブ海峡を通航する中国籍船や中国に拠点を置くオーナーの船舶の数は全体の動向と同様に減少している。3月には中国企業が運航するタンカーに対する攻撃事案もあり、通航を継続する事業者は限られる。
・パナマ運河も水不足から航行制限されているとのことだが、中長期的にコンテナ船が通れなくなる(現状の迂回ルートがメインになるなどの)可能性はあるか。
後藤
パナマ運河は、報告で紹介したように航行制限が強化されたが、水位の回復に伴い制限は緩和される見込みである。今後も乾季に通航制限が強化されることはありうるが、通航自体ができなくなることは考えにくい。
原氏
水資源が問題となる。ガトゥン湖流域の降水量がどうなるか、パナマの人口増と都市化に伴う水利用の増加がポイントとなる。パナマの新政権がどのような対応をとるかが重要で、対策として検討されている工事の場所はパナマ運河庁が管理する区域以外も含まれるため、どういった判断をするか注視したい。
・コンテナ船の大型化について、24,000TEU型が最大船型だが、直近は13-16,000TEUサイズの船型の発注が相次いでいる。コンテナ船の大型化は24,000TEU型で頭打ちとなったのか。また、次世代燃料船が増えるなか、これからのコンテナ船の主力船型はどのぐらいのサイズになるか。
松田氏
現在行っている共同研究の結果では、海運会社は大型化のインセンティブがあるため、制約を考慮しても27,000TEU型までは大きくなりうると考えられる。ただ主力船型になるかは別の話で、個人的な見解だが主力船型となるのは汎用性が高いネオパナマックスサイズではないか。
原氏
工学的な最大船型と運航する主体からみた経済性での最大船型の二点を考える必要がある。経済合理性の話をすると、『コンテナ物語』の著者であるマルク・レビンソンは「大型船の時代は終わった」と述べた。デカップリングやニアショアリングを織り込んだ見方だと考えられる。一方で、荷動きは世界全体で伸びており局地的に著しい成長をしている地域があり、船幅需要も増加する。27,000TEU型がどういう船かというと、資料内のアジアから欧州の平均船型を1万TEU上回る。この船腹量の増加に見合った輸送量の伸びがあれば、大型船の効果が発揮される。
汎用船型に関しては、どこでも差し向けられる船型のニーズは高まると考える。インド、中南米、アフリカに配船できる船舶、レンジがあるが、18,000TEU型は一つの目安となると考える。北米東岸の港湾にCMA-CGMが投資をしており、アジアと北米東岸間に2万TEU以上のコンテナ船を投入することを構想しているとの報道がある。こうしたこともポイントになると考える。
4.視聴者・来場者からの質問
・インド中東地域の貨物が伸びているとのことだが、港湾への投資や設備はどのような状況か。喜望峰への迂回が増えており船腹の需給ギャップがあるが、不足分をどのように手当てしているのか。
原氏回答
インドの港湾について、ターミナルの整備、鉄道や道路など内陸輸送との接続、蔵置スペースの確保が課題となる。2万TEU以上のコンテナ船が寄港できる港湾はないと記憶しており、整備が進めば局面も変化するだろう。船をどこからもってくるのかについては、目下は供給過多となっている航路から転配している。
・パナマ運河について、代替ルートの開発状況をお教えいただきたい。
後藤回答
資料にあるように中米地域では、複数のドライキャナル構想があり、検討・開発がすすめられている。設備が十分ではないうえ、2度の積替えが発生し、内陸輸送の容量や費用など課題が存在する。代替的な手段を果たすことは難しいと考えるが、輸出入の拡大や産業振興など当該地域の経済には裨益するだろう。
・CIIの関係で減速航行をしているかと思う、現在の事態が長期化した場合、新造船の竣工もあるが、船腹量のバランスはどのように推移するか。
原氏回答
船の捻出するための一つの方法として増速があると認識している。ただこれには限界があり、船腹量のバランスがどうなるかは不透明である。EU-ETSを視野にいれる必要もあるため、様々なことを考慮しての判断となる。
・コロナ禍以降、荷主の最適在庫の在り方が変化していることが、今回の両運河での事象の対応に影響を与えたか。
原氏回答
迂回によって船が遅れたが、在庫を厚くしていたことでラインの停止が防げたといった効果はあったと思う。
・コンテナ船の大型化や主力船型の話に関連して、大型のコンテナ船が日本の港湾へ寄港することは難しい。日本の港湾の目指すべき在り方をどのようにお考えか。
原氏回答
どういう船型が良いのかという考えを共有することはできると思う。港湾ごとに役割は異なり、利用する荷主の調達・生産・販売の方針がある。こうしたことをふまえて、現在と将来の貨物量に応じた形になるだろう。
私見だが、大型化を志向するかに関しては、ネットワークで勝負をするエリアもあるかと思う、日本の輸出入でどの地域を向いているのか、対アジアなど貿易の規模によっても制約がある。1万TEU以上だと大きすぎることも有り得るし、ネットワークを増やして5~6,000TEU型を活用することも一つの方法と考える。
・船腹の需給ギャップが生じていることは、コンテナ船社が調整をしている過程であり、現在は非効率な状態ということか。
原氏回答
結果として、必要なだけの船腹量が投入できていない航路があることは事実としてある。しかし、コンテナ航路の運営は過去の行動に束縛される側面もあり、時間をかけて解決することだと考える。
(注)以上の講演の結果概要につきましては、主催者側があくまで速報性を重視して作成したものですので、発言のニュアンス等を正確に再現できていない個所、あるいは重要な発言が欠落している箇所等がある可能性があります。
つきましては、発言の詳細や正確な発言を確認したい場合は必ずYouTubeを視聴してご確認いただくようお願いします。また、本結果概要の無断での転載等は控えていただくようお願いいたします。



