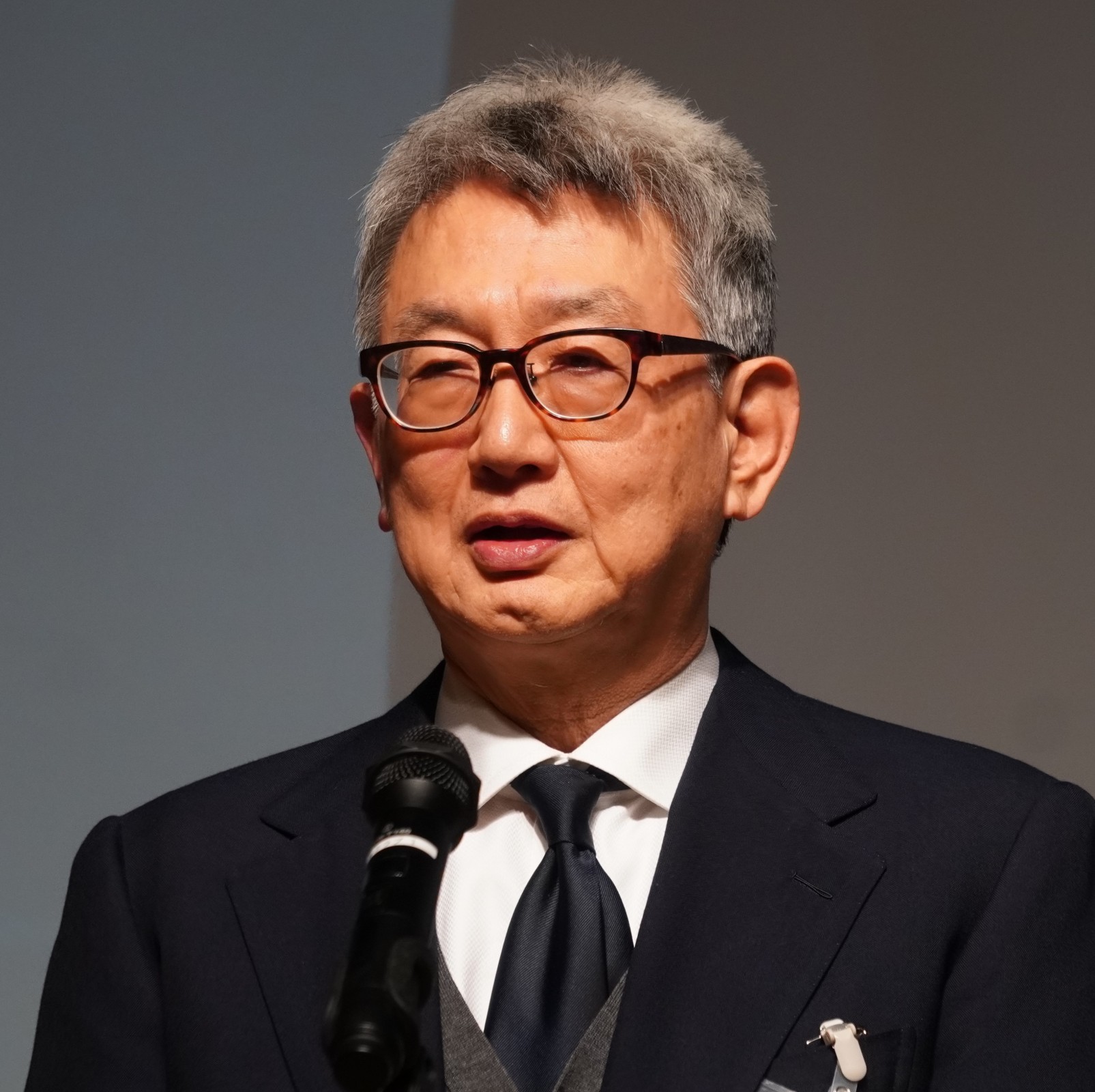第35回海事立国フォーラム in 東京 2025
「海事産業のデジタル化・グリーン化に向けた海事人材の確保・育成」
 |
|
 |
|
| 開催概要 | 我が国は急速な少子高齢化の進行と人口減少の状況下で、海事産業を支える海事人材については、外航海運を担う大手船社は海外で自営の商船大学により船員養成を行うなどの取組を行う一方、内航海運業界は船員の高齢化に対処すべく積極的に若手船員を採用するなどの努力を重ねている。 さらに、自動運航・遠隔監視といったデジタル新技術の活用やアンモニア、水素等の新たな燃料の導入を見据えて、DX・GXの新技術に対応できるスキルを有する船員やその教育者、および陸上の海事技術者や海事・海洋分野の研究者を含めた海事人材の確保・育成も急務となっており、このような人材の確保・育成は、海事産業の競争力向上にとって重要な基盤要件である。 そこで、今回の海事立国フォーラムでは、このような海事産業を巡る環境変化の中で、今後の海事産業強化の観点から必要とされる人材確保と育成に向けた取組等について意見交換を行うことを主たる目的とした。 |
| 日時 | 2025年2月5日(水) 13:30 ~ 18:00 |
| 開催方法 | 実開催(YouTube配信あり) YouTube視聴用URL:https://www.youtube.com/live/T5DRN5epS0I ※YouTubeで視聴いただく場合は、お申込は不要です。 |
| 開催場所 | 海運ビル 2階国際ホール (〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-4) |
| 主催 | 公益財団法人 日本海事センター |
| 後援 | 国土交通省 |
| 開会挨拶 | |
| 基調講演 | |
| 講演1 | |
| 講演2 | |
| 講演3 | |
| 講演4 | |
| 講演5 | |
| パネルディスカッション |
 |
| 閉会挨拶 | |
| フォーラム動画 (通し) |
https://www.youtube.com/watch?v=Fv5ai9pyq3E |
第35回海事立国フォーラム in 東京 2025の開催結果(概要)
◆開催日:令和7年2月5日(水)
◆場 所:海運ビル国際ホール 東京都千代田区平河町2-6-4
◆主 催:(公財)日本海事センター
◆後 援:国土交通省
【開会挨拶】
(公財)日本海事センター 会長 宿利 正史
(別添参照)
【基調講演】「海事産業の強化に向けた海事人材の確保・育成」
国土交通省海事局長 宮武 宜史 氏
海事人材に係る現状について、内航船員数および外航船員数の推移と傾向、マネジメントなど船員に求められる能力の変化、船舶の新燃料等や自動運航船など新しい動向と適応の必要性、船員養成課程及び船員養成機関や水産高校の現状、船員の労働時間と有効求人倍率の変化、船員の働き方改革や女性船員の活躍推進の取組みについて説明がありました。
また、今後の海技人材の確保のあり方と取組みに関する検討会のとりまとめの概要や、公共職業安定所等・地方運輸局等のモデル連携事業、快適な海上労働環境形成の促進に資する仕組みの導入、(独)海技教育機構の中期的なあり方に関する検討状況などについての説明がありました。
【講演1】「自動運航船社会実装に向けた今後の展望と人材育成」
東京海洋大学学術研究院海洋電子工学部門教授 清水 悦郎 氏
自動運航船についての説明と研究開発の背景ならびに国内外における実装に向けた検討スケジュール・取組み状況の説明の後、Oceanic Constellations社、JMU Group、MEGURI2040、Zeabuz社およびZeam社、Ocean Infinity社、US Navyなど国内外における自動運航船の最新の開発動向について説明がありました。
続いて、状況認識システムの開発既存の国際条約への技術面での対応、水路地図の4D化・高精度化の研究開発、安全評価・基準制定手法の確立など自動運航船社会実装に向けた技術開発課題についての説明と自動運航船に必要となる人材と東京海洋大学における今後の取組の説明がありました。
【講演2】「代替燃料船の導入に向けた海事人材の確保と育成」
(一財)日本海事協会認証・海技部長 斎藤 直樹 氏
今後の代替燃料船の安全運航へ向けた人材の前提条件について説明した後、代替燃料船のトレンド、IMOのGHG削減戦略へ向けた船員の再教育の必要性と解決すべき課題、IMOにおける代替燃料船の船員に関する議論、STCW条約の包括見直しに係る動向、今後の世界の船員マーケットにおける船員(特に職員)の不足の可能性、船主団体が主導するIMOへの新たな提案、実際のオペレーションに必要な訓練への動きに関する説明と代替燃料船に必要な能力についての整理がなされました。
続いて、船舶管理の視点から、どの人材から教育訓練していくのが効率的なのか、どんな教育訓練が必要なのか、代替燃料船時代に向けて船員獲得は可能なのかという点についての説明と日本海事協会の活動に関する説明がありました。
【講演3】「外航海運業における人材の確保と育成」
(一社)日本船主協会副会長 土屋 恵嗣 氏
外航海運の現状、外航海運海技者の業務、技術者集団としての役割について説明の後、外航海運のドル建て比率の高さや歴史的経緯も踏まえつつ、日本人海技者の確保・育成のための官民の取組み、フィリピン等における外国人海技者の確保・育成のための日本の取組みに関する説明がありました。
続いて、GHG排出ゼロ目標を踏まえた新燃料導入に伴う資格取得・訓練による海技者の負担増加や、新燃料船舶への移行についての説明、自律運航船の開発などデジタルトランスフォーメーションに係る動向と法的課題の説明、海技者制度をはじめ海運に関連する制度全体のイコールフッティングの必要の説明がありました。
【講演4】「内航海運業における船員確保と育成」
日本内航海運組合総連合会 藏本 由紀夫 氏
内航海運の現状を踏まえ、内航船の乗り組み基準を紹介したうえで、6級海技士養成奨学金制度の設立および6級海技士短期養成コースが船員不足解消に寄与している点の説明がありました。
続いて、内航船員の新規就業者の主な供給元である商船系高等専門学校や水産高校との連携強化の取組みについての説明がありました。また、女性船員の活躍促進に向けたジェンダーレスな視点による船員対策検討会の設置と取組みについて、内航船員の定着化に向けた調査をもとにした海技教育機構による船員教育・訓練マニュアル等の教材開発及びその活用方法および内航船員確保対策協議会における活動助成についての説明がありました。
【講演5】「JMETSにおける取組と展望」
(独)海技教育機構理事長 田島 哲明 氏
JMETSの概要紹介の後、海技免状の取得である第一種船員養成、上位免状の取得である第二種船員養成、海技大学校における実務教育や水先教育、論文集の刊行、研究発表会の開催を含む研究事業、開発途上国船員養成事業や国際会議への専門家派遣などの国際業務など、JMETSの事業について説明がありました。
続いて、LNG船の就航を踏まえたIGFコードに対応する訓練の実施、無人運航船プロジェクト「MEGURI 2040」における船員スキル定量化事業の実施、その他GX・DXに係る受託研究等の実施などJMETSにおけるGX・DXに係る活動についての説明の後、船員教育訓練を充実させるための資金確保に向けたネーミングライツ事業、賛助会員制度の紹介がありました。
【パネルディスカッション】
モデレーター:(公財)日本海事センター海運問題研究会会長・海事人材問題委員長/
神戸大学大学院リサーチフェロー 羽原 敬二 氏
パネリスト:講演者6名
〇冒頭あいさつ
羽原氏より、「産学官のリーダーの方々から話を伺ってきましたが、その話を掘り下げるとともに、今後の展望について洞察を深めていきたいと思います。」との冒頭あいさつがなされた。
テーマⅠ:今後求める海事人材とは?
〇羽原氏
講演でも触れられたが、「海技人材の確保のあり方委員会」において今後外航・内航業界で求める人材像が少しずつ明確になってきたと思うが、土屋副会長と藏本副会長から、個人的な意見も含めて、端的に業界としてどんな人物を求めているのか、もう少し敷衍するコメントをいただきたい
○土屋副会長
外航海運では、STCW条約があり3級海技士の養成は前提となる。これから燃料が転換するなかで、海事人材の正解はひとつではなく、様々なタイプの燃料、運航形態があるなかで、高い水準での専門人材の育成が求められる。
〇藏本副会長
内航については、大型船と小型船で人材像が異なる。船員問題は、小型船がメインである。私も乗船経験があるが、そのような船は特にコミュニケーション能力、忍耐力が求められる。技術革新の進展と省人化が求められるが、緊急時、トラブルに対応できる知識や柔軟性が求められる。教育体系の整備は、官や関連団体のみならず企業や組織として必要となる。
〇羽原氏
土屋副会長と藏元副会長のコメントを頂戴したが、新燃料対応について斎藤部長からコメントをお願いしたい。
〇斎藤部長
脱炭素対応に関し、他産業と海事産業の違いを考えた際に、専門人材の確保という点で、現在活躍している方にトレーニングをして、専門人材となってもらう必要がある点が大きな違いだと認識している。仕事に従事しながら新しいことを学習する必要がある。人手不足は今後も課題となるが、脱炭素については、対応できる組織やチームをつくること、ノンテクニカルスキルが運航面では重要ではないかと思う。新燃料に向けた訓練を前向きにやっていく環境、雰囲気を作れるかどうかは、鍵となるだろう。
テーマⅡ:どうすれば海事人材を確保できるか?
〇羽原氏
業界として、海事の仕事にもっと興味を持ってもらい、どうすれば必要な人材を確保できるのか、宮武局長、土屋副会長、藏元副会長に感想や意見などをお話しいただきたい。
〇宮武海事局長
海事の世界は国民全体にあまり知られていない中で、関心を持ってもらう地道な努力が必要となる。若いうちからのアプローチをはじめ、継続して取り組むべきだと考える。海に面した自治体の数をみると西日本は多く、海事の仕事とのつながりも比較的あるが、東日本の自治体でも少しでもきっかけをつくり、そこから関心を持ってもらうことが重要だと考える。
〇土屋副会長
若年層へのアプローチの重要性は理解しており、海事産業の存在や意義を早いうちに理解してもらうための取組みを行っているところである。学習指導要領において、海事思想の普及がより充実した内容となることを求めているが、人材確保の観点では、職業選択の年齢が高くなっている中で、一般大学から海技大学校に進学して海事の道へ進むといったように新3級制度に期待している。
〇藏本副会長
内航船員の出身地に関する情報からも、幼少期の環境が重要だと思われる。内航総連においてWEB調査を行ったが、回答者の9割以上が内航業界を知らないという結果だった。今後も陸上からの転職に目を向けないといけないが、前職で何が不満だったか、そのことは海上で解消できるか等について知ったうえで対策を考える必要がある。年齢や性別を問わずターゲットを広くすることや、定着率に課題がある中で、人間関係を築くためのマニュアルづくりといったことの取り組みを拡大したい。
テーマⅢ:どのようにして優秀な人材を育成していくか?
〇羽原氏
海や船に関心を持っていただいた若者をいかに教育していくべきかについて教育の側から田島理事長と清水教授からコメントをいただきたい。
〇田島理事長
独立行政法人は、民間に任すと実施されないことを国から分割した組織に任せるという建付けとなっている。そのため、役割分担を確認しなければならない立場である。海事人材を取り巻く環境が変わる中で、マインドセットを変え、練習船の体制等点検・見直しをする時期だと考えている。今後はさらに社船実習の拡大を考えたい。業界大手では、3級海技士の乗船実習12ヶ月のうち後半6ヶ月を 社船、内航のフェリーでは、最後の3ヶ月を社船で行うケースや、4級海技士養成課程では、乗船実習9ヶ月のうち最後の3ヶ月を社船で行うケースがある。社船実習の拡大のために、何が必要かを今後考えたい。
〇清水教授
まず、海運業界の知名度が低いと感じる。学生の人気就職先に入っているかというと、そうでなく馴染みがない。職業選択の時期が遅くなっている中で、改めて船員という職業を知った人が、現在はスキルが高度化して、技術的に進んでいる職業であると考え、大学・大学院を出て船に乗りたいと考えた時に、雇う側としては就職時の年齢が上がるが、そういう人材が躊躇せずに活躍できる場を設けていただきたい。例えば、給与面でも現在は学部卒と院卒で変わらないと思うが、大学院卒の給与水準を引き上げるなど大学院出身者が入るような体制を作る必要があると思う。
テーマⅣ:今後さらに必要となる対策は?
〇羽原氏
最後に、今後必要となる対策について、今でもいろんな取組がなされているが、業界や教育機関で対応するだけでは限界があり、やはり産官学の関係者が一体となり、一丸となって対応していく必要があるのではないかと思う。
その点で、土屋副会長、藏本副会長、そして清水教授、斎藤部長、田島理事長、最後に宮武局長の順でコメントをいただきたい。
〇土屋副会長
海事関係団体はそれぞれ広報活動を熱心に展開しているが、更なる横の連携が必要と考えており、海事局の旗振りで連携強化を図っていただきたい。船主協会においても、広報活動が複数進行中である。海事人材の確保について、海事局においては、高い視野に立った船員政策を進めていただきたい。
〇藏本副会長
陸上と海上の賃金を比較して、近年は陸上のほうがとても上がっている。やはり、賃金を上げるためには、事業者が適正な料金を収受することが重要である。また、新燃料対応など船員に対する新たな教育が必要となる中で、スキルアップできる環境をつくる必要がある。さらに船員の職業を知ってもらうために、ハロワークと運輸局を接続することや陸上から海上に転職する人に対する職業訓練をできる環境が必要となる。資格取得の期間短縮についても安全を担保したうえで、現在より短期で資格取得できるようにできればと考えている。
〇清水教授
自動車業界やコンサルティング業界にいた方が、海事産業に入る例がある。海事産業を広めることや知名度のアップは不可欠だと考える。教育機関側の立場として、大学院におけるスキルアップ、キャリアアップの環境を整えることや大学院を出た方を積極的に採用することも事業者には考えていただきたい。
〇斎藤部長
代替燃料船について、人材の確保育成は重要なピースである。業界全体で再教育に向かう必要があるが、幸いまだ時間の余裕はある。技術サイドの連携に関して、得意なところを出すことももちろんだが、不得意な点にも取り組む必要があると考える。脱炭素、自律運航で海事産業の変革に関する取り組みは終わる訳ではない。海事協会として、新しい海運界の挑戦の一翼を担いたい。それが若い世代を取り込んでいくことにつながると考える。
〇田島理事長
必要な対策というよりも率直なお願いとなるが、人手不足である中、自助努力はもちろんだが、民間から人を出して現場を助けていただきたいと思う。海運事業者から若手の人材を提供してもらい練習船の教官をしていただいている。実業の経験が多くない教官にも貴重な経験となっている。また、舶用メーカーから講師として来ていただくこともある。実業界から船や学校の現場に入っていただいて、アドバイス・お手伝いをしていただきたい。片務的なお願いとなるが、社会貢献の一環として、事業者の方々には検討いただきたいと考えている。
〇宮武局長
今回頂いた提案も踏まえ、海事局における取り組みを確実に実行に移したい。それぞれのプレイヤーが壁を作るのではなく、互いに寄り添って対応することが重要だろう。それぞれが対応範囲を絞ると隙間に落ちる部分が出てくるため、持ち場を一歩増やして取り組みを進めることで一体感が出るだろうと考える。
〇羽原氏
自動運航船や新燃料船に関して追加的なコメントはあるか。
○清水教授
新燃料のバンカリングや自動運航船での荷役や出入港など課題はたくさんある。船単体ではなく、港湾や陸上の物流を含めた対応が求められる。分野横断的な対応やその環境づくりが求められると考える。
○藏本副会長
トリプル連結バージに関する検討会をしている。切り離した後のバージが船舶かどうかといったことや安全が担保できるか等様々な論点がある。実際に新たな船舶を作っても規制が障壁をなることがあるため、行政では、新しい技術の促進も念頭に置いて合理的な新しい規制を考えていただきたい。
○宮武局長
カーボンニュートラルや自動運航においては、港湾をはじめ色々なプレイヤーとの接点が出てくるため、縦割り意識をなくしたい。また、規制の在り方について技術が進歩する一方で規制が壁となってはならないが、目配りができてない部分はある。その部分については、声を上げていただきたい。バージの話など細部まで把握できていない部分もある。
会場からの質問
〇質問1
海事人材の概念について、職業としての船員と船員以外の方を念頭に置いている場合があるように思う。海技資格を持ちながら研究を行っている方もおり、練習船での実習なども仕事に生きているのではないか。
〇羽原氏
海事人材は船員などの海技者だけでなく、もっと広い概念であるが、定義付けは難しい。
〇質問2
外航海運に関しては、外国人材を活用している。内航船に関しても、間口を広げるという意味で、活用を検討されたらどうか。造船業では既に多くの外国人材が存在する。何が問題となるのか、お伺いしたい。
○宮武局長
海運事業者の一部の方からも外国人材の活用について要望があると承知している。ただ、内航に来てくれるかという問題がある。造船業でも他国との人材獲得競争が発生している。海事において外航というライバルがあって、あえて日本の内航業界で働く外国人がどれほどいるのだろうか。世界の海運マーケットの中で、内航船員不足において外国人材が解決策となるか疑問である。まずは、日本人の確保育成に注力する方針である。
○清水教授
日本の教育機関として、日本人船員の確保育成は重要であると考えている。政治的なリスク、国民の安全確保という観点から物資輸送にどれくらいの人材が必要か、日本人が働きやすい環境作りをまず考える必要がある。荷主から適正な料金を収受し、賃金水準を上げる努力、物流を守るという意識が重要である。
〇質問3
船員という職業があまり知られていないというなかで、取り組みとして、船員の日を活用されたほうが良いのではないか。2010年のSTCW条約の改正の際に決議されたもので、6月25日が船員の日となった。船員に敬意を示す日であるが、知ったのは欧州の管理会社の方からの連絡がきっかけだった。国連が決めた日であり、海外では一般的だと思うが国内では全く広まっていない。船員の日について産官学で活動することで、船員の貢献が一般に知られることにより、やりがいも生まれると考える。船員の日を広めることも重要ではないか。
〇宮武局長
わたしも正直知らなかった。今後の検討課題だと思う。
〇質問4
次世代燃料や自動運航船について、人材面では日本がリードしているとは言い難く、条約対応に留まっていると認識している。海外の事情についてお伺いしたい。
○斎藤部長
シンガポールでは、MPAがトレーニングパッケージをつくっている。対面式が必須の内容となっており、船員向け、管理会社向けの教育を募り、シンガポールに人が来る仕組みを作った。注目すべき事例だと考える。
【閉会挨拶】 (公財)日本海事センター理事長 平垣内 久隆
(添付参照)
(注)
この結果概要は速報性を重視し、事務局の責任で編集しているものであり、発言内容の取り上げ不足やニュアンスが異なる場合がありますので、正確な内容については必ず画像及び音声をご確認いただくようにお願いします。